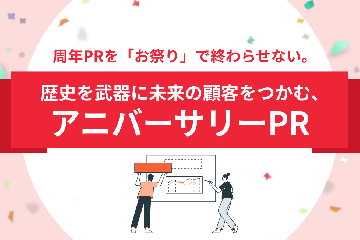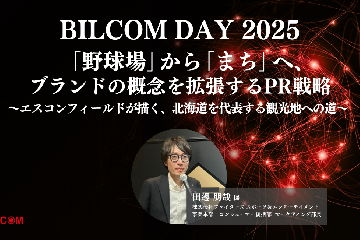PR BLOG
PRブログ
- 2024年12月03日
- PRノウハウ 、セミナーレポート
BtoB企業の攻めのブランドコミュニケーション ~統合新会社レゾナックの事例から学ぶ~
2024年10月11日、当社が主催するPRカンファレンス「BILCOM DAY 2024」を開催しました。今回は、BILCOM DAY 2024内で行った「BtoB企業の攻めのブランドコミュニケーション ~統合新会社レゾナックの事例から学ぶ~」のセミナーレポートをお届けします。
■ゲスト
京都精華大学特任准教授/ブランディング・ストラテジスト
(元レゾナック・ホールディングス ブランド・コミュニケーション部長)
山田亜紀子 氏
大学卒業後、朝日新聞社に入社。記者、編集者を経て草創期のデジタルメディアで広報宣伝や新媒体立ち上げプロジェクトを複数経験。ソーシャルメディアエディター、新規事業統括担当等。 2020年退職。途中、立ち上げ期のNewsPicksに”留職”。その後、再エネベンチャーの広報マネージャーを経て、22年4月から24年7月までレゾナック・ホールディングスのブランド・コミュニケーション部長。旧日立化成と昭和電工の2社統合・社名変更にあたり、広報宣伝責任者としてリブランディングを担当。 24年7月末退職。22年4月より現職。
皆さまこんにちは。本日はBtoB企業のブランドコミュニケーションについてお話しさせていただきます。
レゾナックでは、新会社の浸透とブランドイメージ構築に注力し、その結果、発足から1年足らずで日本最大規模のブランド価値評価調査「ブランド・ジャパン2024」へノミネートされました。また、一般財団法人経済広報センターが主催する第40回企業広報賞では、「企業広報経営者賞」を受賞しました。このような経験を踏まえ、レゾナックという新会社発足に至るまでの活動や実際に行ったPR戦略についてご紹介します。

レゾナックに参画。新会社発足までの想い
私がレゾナックに参画したのは、ちょうど昭和電工が日立化成と統合が決まり、レゾナックという社名が決まった後でした。2023年1月の新会社発足まで8ヶ月ほどしかなく、この先どのようにブランドコミュニケーションを行っていくか、早急に計画を立てる必要がありました。昭和電工は石油化学や化学品を扱う総合化学メーカーでしたが、積極的な広報活動はほぼ行っておらず、プレスリリースを出してお問い合わせを受ける、といった受け身の体制でした。過去メディアへの露出はほぼないという状況でしたので、新社名になり、社名認知が0になる可能性を経営陣も危惧していました。
リブランディングに広告は必要?レゾナックのブランディング手法
私が入社した時点で、昭和電工という社名は7割弱に認知されていましたが、その中で事業を正しく認知している方はわずか10数%で、半数近くはイメージがない、という状況でした。このような中で当時のメンバーは、広告代理店からCM放映を提案され、CMの力で認知度を上げる重要性や、認知度の高い他社の広告予算事例などの説明を受けていました。しかし、私の中には「BtoB企業でもあり、本当にそこまでのCMが必要なのか?」といった疑問がありました。
まずは、経営陣や社内関係者と認識を統一することが重要であると考えました。ひとつだけ、認識を一致させることができたのは「社名連呼によって、社名だけを覚えてもらっても意味がない」という点です。これを議論の土台としつつ、一番大切だと思っていたのは、企業の土台としてのストーリー構築です。経営戦略をリードする「ブランド・ストーリー」を作り、それを社会文脈の中に位置づけ、CXOの誰が何を語るかを決める必要がありました。
当時から、レゾナックは中期の経営戦略のなかで「2030年には世界トップクラスの機能性化学メーカーになり、その手前の2025年には半導体材料の世界企業リーディングカンパニーになる」という目標を掲げていました。一方、レゾナックの社名の由来ともなった「共創型化学会社」という企業姿勢を伝えることが大事だという考えも、経営陣やブランド部門のメンバーの中に根強くありました。
レゾナックは、英語の「RESONATE」(共鳴する・響き渡る)と、「CHEMISTRY」の「C」を組み合わせてできた社名です。統合が決まった後、議論のうえで社名やパーパスを決めてきた経営陣とブランド部門、広告代理店は、これを広げることを大切にしていたのです。しかし、いきなり「共創型化学」というレゾナックの企業姿勢を発信しても世の中には伝わりづらいと考え、一旦優先順位を下げて、統合前の広報活動では、半導体という事業内容を伝えることに注力しました。
新ブランドに必要なストーリー発信とは
レゾナックという新ブランドを発信していくにあたり、半導体という馴染みのないカテゴリーを、どのように伝えればいいか。メディアや一般の方々に理解してもらいやすいストーリーとして、「日本は半導体のデバイスは世界で負けたが、材料分野では世界トップシェアを維持している」という事実にフォーカスしました。
このテーマに絞ったのは、社会的な文脈を意識したからです。2020年から2021年にかけて、自動車メーカーなどの半導体不足や半導体に関する地政学リスクに関する報道もあり、半導体分野が徐々に注目されるようになりました。2021年11月には、経済産業省から「半導体・デジタル戦略」が発表されました。半導体はこれからの暮らしを支えるキーテクノロジーでもあります。その半導体市場において、日本の化学企業が縁の下として技術革新を支えており、レゾナックもその一端を担っているというストーリーを展開しました。
しかし、私が入社する前までの経営戦略や対外発信では自社を「機能性化学メーカー」と定義していたため、「半導体の会社」と言い切ってしまっていいのかという悩みは残っていました。さらに、自社のカテゴリを半導体材料と定めるのか、またはレゾナックが世界No.1だと言える半導体後工程まで絞るのか。企業としてどこまで絞り込むかが重要なポイントでした。最終的には、半導体材料で走り出すことにしました。まずは半導体材料メーカーとしての認知を図り、その後、半導体後工程が半導体部門の中でも非常に要となる部分を担っていることを周知しようと考えました。そして、半導体後工程においてはレゾナックの技術がトップであるという事実を伝えていこうと決めました。こうしたステップを踏むことで、より半導体後工程というカテゴリがわかりやすく認知されると思ったからです。

守りから攻めの広報へ。広報体制の強化
そのためには、業界誌の取材対応だけでなく、主要メディアとの密なコミュニケーションが重要です。守りの広報から攻めの広報へと変革するためには、レゾナックとして広報の仕組みを育てることが重要であると考えました。真っ先に実施したのは、半導体PRに関する社内横軸プロジェクトの発足です。事業部や経営企画室が一体となり、役員も交えたプロジェクトチーム「半導体PR戦略プロジェクト」を立ち上げました。
そして、まずは業界のことを理解していただくため、メディアに向けた勉強会を開催していきました。世界的な半導体市場の状況、キーテクノロジーである理由、生活者にとっての意味、「素材」の技術動向、製品シェアなど、自社だけでなく業界全体の内容を解説する資料(ファクトブック)を事業部の協力も得て作成しました。こうした半導体全般の勉強会を行ったことで、メディアに「半導体のことならレゾナックに聞こう」と思っていただけるような関係性とポジションを目指しました。その結果、化学業界の記者だけでなく、従来はお声がけしていなかったWebメディアや半導体業界の記者にも取材していただけるようになりました。
新会社発足会見を実施。半導体材料メーカーとしての第一想起を狙う
そうした何度かの半導体説明会を経て、新会社の発足直後の会見では、「世界的な半導体材料メーカーが誕生した」ことを強調しました。これにより、主要メディアの記事タイトルも半導体に関する内容を中心に掲載いただき、半導体材料の新会社として、経済紙やWebメディアなど多くのメディアへ露出することができました。まずは「広報活動を通して半導体材料メーカーとしての第一想起を狙いたい」、という目標は、無事に達成できました。宣伝活動については次のステップで本格的に始動させようと考えていました。
メディア露出においては、誰が語るか、つまり「会社の顔づくり」が重要です。CEO、CFO、CSO(最高戦略責任者)など様々な役職、経験を持った方が揃う中で、まずは半導体企業で長年のキャリアがある真岡朋光CSOを「半導体分野の専門家・実務家」と位置付けてメディアへ売り込み、レゾナックが半導体分野のキープレーヤーであるという印象を形成しました。
また、企業を変えるスピード変革者として、高橋秀仁CEOもメディアへの登場機会を増やし、新会社にかける想いやビジョンを自身の言葉で語ってもらい、新しいタイプのリーダー像として世の中へ印象づけました。高橋CEOは2023年だけで主要メディアにのべ22回登場し、取材いただいたメディアからは、「新時代の到来、期待を感じさせる」といったお声もいただきました。
メディアへの露出が成功した理由のひとつとして、経営者が、自らの言葉で語る人だったことも大きいと考えています。記者は自分の言葉で語る経営者を求めています。私の新聞社時代の経験を踏まえて、CEOがみずからの言葉で話しやすい媒体や枠選びをしたことも、取材してくださるメディアが増えた秘訣だと思います。
ソーシャルメディアは、人的負荷が大きいですし、リスク管理や経験も必要なので、レゾナックにおいてはサードステップとして考えていました。一方、オウンドメディアは自分たちの発信したいことを発信できる場で、アーンドやペイドからの誘導先になるとともに、メディアへの説明材料としても有効だと考えています。
セカンドステップで統合キャンペーン。広告・タイアップ・アーンドを組み合わせる
新会社発足までとその後しばらくは広報活動、メディアへの露出を増やすことに注力しました。一定程度、メディアでの報道が獲得できた後、2023年11月に統合キャンペーンを実施することを計画しました。新卒の採用活動を意識し、このタイミングを決めました。そこから逆算し、イメージづくりのCMも、ファクトベースのメディア発信も、「半導体事業は日本復権のチャンスであり、勝ち筋は半導体後工程材料にある」といったことを発信していきました。アメリカのシリコンバレーに拠点を設けるというニュースも、あえて、このタイミングに合わせて発表しました。
こうした企業のニュースは、自分たちの言葉でなく第三者発信で世の中に浸透させていくことが非常に重要だと考えています。記者発表のタイミングやCM放映にあわせてメディアと専門家による発信が実現でき、露出の量も担保することができました。専門家の方が興味を持って色々な場面でレゾナックの事業や半導体についてお話しくださったり、媒体のコラムを持っている先生方からお墨付きをいただいたりしたことで、想定以上に副次的なメディア露出効果がありました。結果、新社名の認知度は社名変更から1年で3割を超え、報道量を大きく増やすことにも成功しました。
BtoBブランディングにおいて重要なこと
私がブランディングにおいて重要だと思うのは、社外に何を発信するか優先順位を決め、社内でコンセンサスを取りながら遂行していくことです。また、もともと世の中での認知がある企業でないと、パーパスだけで共感を得ることは難しいと思います。企業の存在意義やパーパスはインナーブランディングとして力を入れ、社外には、社会や市場起点での事業活動のファクトを発信していくこと、それを通じて会社の存在意義を伝えることが重要だと考えています。
今後、ブランディングを行っていくマーケターや広報担当者の方々に、私の経験が少しでもお役に立てば嬉しく思います。本日はご清聴いただき、ありがとうございました。
ビルコムは、企業の独自価値に着目しながら、事業に貢献するコミュニケーション施策を行う会社です。リブランディングや企業の認知向上など、お気軽にご相談ください。
書き手:コーポレートコミュニケーション局 川島弓奈