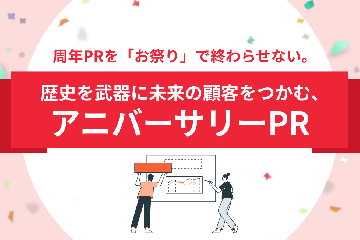PR BLOG
PRブログ
- 2025年10月16日
- PRトレンド 、PRノウハウ
代替食品のPR成功事例を徹底分析!市場で認知を広げるコミュニケーション戦略とは?
2025年10月に入り、乳製品や調味料、冷凍食品など、私たちの生活に身近な多くの食品が再び値上げされました。日々の買い物で、家計への負担を実感されている方も多いのではないでしょうか。このような状況は、消費者の購買行動に大きな変化をもたらしています。そして今、「節約」という新しい視点から、これまでとは異なる理由で「代替食品」が大きな注目を集めているのです。
もともと代替食品は、「健康志向」や「環境配慮」といった価値観を背景に市場を拡大してきました。2025年4月に富士経済社が行った、代替タンパク食品の国内市場調査によると、2030年には市場が1,473億円規模に達すると予測されています。
2025年4月15日 富士経済グループプレスリリース「代替乳や微細藻類、代替肉などの代替タンパク食品をはじめとしたサスティナブルフードと関連装置・サービス市場を調査」
しかし、相次ぐ食品値上げを受け、「従来のお肉やお魚よりも手頃な価格でタンパク質を摂れる」という経済的なメリットが、消費者の選択を後押しする新たな動機となりつつあります。市場拡大の裏側には、こうした消費者のインサイトの変化を捉えた、優れたPR戦略があります。本記事では、国内外の代替食品のPR成功事例を分析し、市場で認知を広げるための共通項と、効果的な4つの戦略的アプローチを解説します。
1. なぜ今、代替食品の「伝え方」が重要なのか?
前述の通り、代替食品市場は「健康・環境」への貢献という追い風に加え、「経済性」という新たな追い風を受けています。しかし、多くの消費者は美味しさへの不安や価格への抵抗感を抱えています。2024年8月に情報サイト「ファンくる」が行った代替食品・飲料(米粉や大豆ミート、オーツミルクなど)に関する意識調査では、最も多かったイメージが「健康に良さそう」61%、「価格が高そう」38%、「美味しくなさそう」28%という結果になっています。
この「期待」と「不安」が混在する市場だからこそ、消費者の心に寄り添い、不安を解消して新しい食の価値を提示するPR戦略が、事業の成否を分ける重要な鍵となっているのです。
2. 【事例で学ぶ】代替食品のPR成功に導くアプローチ
成功している企業は、どのようなアプローチで消費者に語りかけているのでしょうか。代表的な3つの戦略を具体的な事例とともに見ていきましょう。
アプローチ1:いつもの食卓に溶け込む【食文化接続型】
奇抜さや目新しさではなく、日本の家庭に馴染み深い料理での活用法を具体的に提案することで、活用のハードルを下げる戦略です。
味噌メーカーとして知名度と信頼を持つマルコメは、「大豆のお肉」をハンバーグや麻婆豆腐、回鍋肉といった日本の家庭料理にすぐ使えるミンチタイプやフィレタイプで展開しています。スーパーの精肉売り場や大豆製品売り場に商品を並べ、レシピサイトと連携することで、「特別なものではなく、いつもの食材の新しい選択肢」であることを伝えて浸透させています。消費者に新しい行動を求めるのではなく、既存の食生活の中に自然に入れる「身近さ」と「手軽さ」が鍵となっています。
アプローチ2:「地球を救う」をメッセージにする【理念訴求型】
製品の機能ではなく、その背景にある社会的な大義やブランドの理念を打ち出して、消費者の価値観に訴えかける戦略です。
「地球を終わらせない。」という強い理念を掲げるネクストミーツは、代替肉の焼肉用セット「NEXTカルビ」「NEXTハラミ」や代替牛丼「NEXT牛丼」、「NEXTバーガー4.0」など、キャッチーな商品を展開しています。事業そのものが地球環境の改善や食糧危機への貢献であると訴求し、環境問題に関心の高いミレニアル世代やZ世代から支持を集めています。SNSでの発信も積極的に行い、ファンコミュニティを形成しています。ユーグレナ社や亀田製菓社とのコラボ商品など、異業種企業とのコラボレーションも推進しています。製品を買うことが、社会や地球にとって良いことであると示すことで、消費を自己表現の一環と捉える層に強く響いています。
アプローチ3:「社会課題」を起点に必要性を伝える【課題解決型】
多くの人が感じている社会の課題と商品を直結させ、「だから今、これが必要なのです」と解決策として提示する戦略です。
無印良品は、世界の人口増に伴う「食糧危機」という大きなテーマを背景に「コオロギせんべい」を発売しています。昆虫食への抵抗感を乗り越え、発売と同時に大きな話題となり、品切れが続出。これは、単なる珍しさだけでなく、無印良品が未来の食糧問題を考えてこの商品を出した、というストーリーと信頼性があったからです。社会課題を考えるきっかけを消費者に提供し、大きな共感を呼びました。消費者が潜在的に感じている課題意識を顕在化させ、その解決策として商品を位置づけることで、納得感と購買動機を生み出しています。
3. 資源枯渇の解決策としての代替シーフード「パンガシウス」
代替食品のPRは、植物由来のものに限りません。水産資源の枯渇や物価高騰といった社会課題を背景に、代替シーフードも注目されています。
絶滅危惧種に指定されているニホンウナギの資源問題は、夏の土用の丑の日が近づくたびにメディアで報じられます。この社会的な関心の高まりを背景に、ナマズの一種である「パンガシウス」が注目を集めています。2025年6月6日の日本経済新聞によると、価格や供給が比較的安定しているパンガシウスの輸入量が急速に増え、2024年は前年比の4割増で、初めて1万トンを超えたそうです。
2025年6月6日 ナマズの仲間「パンガシウス」が食卓に浸透 輸入4割増、白身魚フライ・すしで存在感 - 日本経済新聞
こうした背景から、飲食店でもパンガシウスが提供されるようになっています。くら寿司では、2024年11月から「活〆(じめ)パンガシウス」が定番メニューとなっています。
イオンは、2017年から各店舗でうなぎ風味の蒲焼としてパンガシウスのかば焼きを発売しています。ASC認証(持続可能な養殖)を取得している点をアピールし、美味しさと手頃な価格に加えて、「水産資源を守る」という社会的な価値を消費者に提示しています。社会課題を起点として、新しい市場の必要性を伝えて認知を広げています。
4. 成功事例から見える、これからの代替食品PRの3つの共通項
これまで見てきた事例には、いくつかの共通点があります。
①「代替」ではなく「新しい選択肢」としてのポジショニング
成功しているブランドは、「〇〇の代わり」という消極的な伝え方をしません。「これも美味しい選択肢の一つ」として、従来の食品と対等な立場で魅力を語っています。
②共感の醸成
なぜこの商品を開発したのか、この商品を選ぶことでどんな未来に貢献できるのか。製品スペックの裏側にあるストーリーを語ることが、価格や味だけでは動かない消費者の心を掴みます。
③オンラインとオフラインを連携させた体験の創出
SNSで話題を作り、飲食店などで実際に味わってもらう。このサイクルを通じて認知から体験、そしてファン化へと繋げています。
代替食品のPRは、単に新商品を売るための活動ではありません。企業の姿勢を社会に示し、消費者の価値観に変化を促し、未来の「当たり前の食文化」を発信していくコミュニケーション活動であると考えられます。
ビルコムは、単なる情報発信に留まらず、データに基づいた戦略的なPR活動を通じて、企業の市場創造を支援しています。 その強みは、独自の診断技術と伝達技術にあります。
診断技術:これまで曖昧になりがちだったブランド力をデータによって可視化します。独自の指標である「PRパワー」の考え方に基づき、当社で開発・提供している広報効果測定ツール「PR Analyzer」の報道データを用いて測定。必要なPR戦略や現在の課題をデータで客観的に確認できます。感覚的だったブランドの概念を明確なデータで捉え、効果的な戦略立案に繋げています。
伝達技術:PRパワーの測定を通じて課題を明確にすることで、次に打つべき効果的なPR戦略のパターンを見出すことができます。ビルコムには20年以上蓄積されたPR戦略の豊富なノウハウがあります。広報業務に関わるデータ分析やメディア露出状況から企業のブランド課題を可視化し、数多くの成功事例に基づいた打ち手のパターンを蓄積しています。
自社の課題を把握したい、あるいはブランド力を高めたいけれど何から始めたらよいか分からない、といった場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
ビルコムへのお問い合わせはこちら
書き手:コーポレート戦略局 川島弓奈