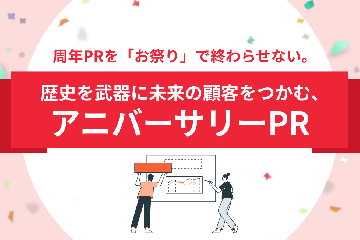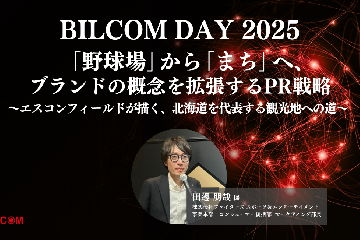PR BLOG
PRブログ
- 2025年08月04日
- PRノウハウ 、セミナーレポート
BtoBブランディングは、広告と広報どちらから始めるべき?~ レゾナックの事例に学ぶ戦略とKPI設計
「ブランディングといえば、まずTVCMが必要?」「広告と広報のどちらをブランディングに活用すべきか悩んでいる」「ブランディングのKPI設計が難しい」このような課題に直面している方は多いのではないでしょうか。
今回は、会社統合・社名変更後わずか1年足らずで「ブランド・ジャパン」新規ノミネートを果たした元レゾナック・ホールディングス ブランド・コミュニケーション部長の山田 亜紀子氏(現:京都精華大学 特任准教授)をゲストにお招きし、「BtoBブランディングは、広告と広報どちらから始めるべき?~ レゾナックの事例に学ぶ戦略とKPI設計」セミナーを開催しました。

登壇者:
京都精華大学特任准教授
元レゾナック・ホールディングス ブランド・コミュニケーション部長
山田 亜紀子 氏
ゼロからの挑戦。新会社レゾナックのブランディング
2023年1月、昭和電工と日立化成の統合によりレゾナックが誕生しました。BtoB企業において、「わざわざ広報や宣伝にお金をかける必要はない」と認識されがちですが、レゾナックは「社名認知ゼロからの挑戦」をスタートさせました。私が参画した2022年4月は、新会社立ち上げに向けて、まさに統合ブランディングが急務だったのです。
正直なところ、当初は「テレビCMありき」といった議論もありました。しかし私自身は、「BtoB企業がブランディングを始めるにあたって、本当にテレビCMから議論を始めるべきなのだろうか」という疑問を抱いていました。社名認知の目標値を設定する際にも、誰に知られるべきなのか、世の中広く認知される必要があるのかどうか、といった点を含め、社内での認識を深くすり合わせる必要性を感じていました。
短期的な「売上貢献」か、長期的な「企業価値向上」か
社内からは、製品の売上貢献を求める声から、長期的なブランド構築の必要性、さらには社内エンゲージメントを高める旗印としてのブランディングの重要性まで、多岐にわたる意見が出ました。
一方、社内でコンセンサスが取れていたのは「レゾナックの前身である昭和電工という会社は、社名認知が7割弱あったにもかかわらず、どんな会社かは全く知られていない」という調査結果が出ていたことと、そのことへの危機感でした。
製品マーケティングとは異なり、コーポレートブランディングとは、会社がどのような方向性を目指して新会社をスタートするのか、そして社員がどのような姿勢でそこに向き合うのかを社内外に示すことで、ステークホルダーからの理解を得るための「企業価値創造」だと考えています。
コミュニケーション戦略とKPI設定のギャップ
コミュニケーション戦略を立案することはできても、それに紐づく「分かりやすく、かつ社内で納得を得られるKPIを設定すること」は、実は非常に難しいことだと痛感しました。短期的に見れば、社名連呼型のCMは認知向上に効果的かもしれませんが、長期的に見た場合に、単なる連呼が本当にブランドとして根付くのかというと、なかなか根付かないと私自身は考えていました。
そこで重視したのは、記憶に残りやすいストーリーの土台をしっかりと構築し、何を伝えていくのかをまず明確にすることでした。社名連呼に頼ることや短期的な記憶にとどまらず、長期的に心に残り、定着するようなものをいかに創り出すかが重要だと考えました。
単に社名が認知されるだけでなく、事業が理解されるだけでもなく、またイメージが先行するのでもなく、認知の先にある、文脈や意味を理解していただく「想起」こそが真の目標であると捉えています。ですから宣伝施策で大きな手を打つ前に広報で土台をつくることが大事だと考え、私が参画して1ヶ月後に「メディアにおける第一想起を獲得すること」を目標として掲げました。新会社発足まで7か月のタイミングでのことです。
広報戦略の核「日本の半導体は負けていない」
とはいえ、「新会社発足」についてなんらかのプロモーションをすることも期待されていました。難しいと感じたのは、新社名を伝えるという使命がある中で、伝えたいメッセージが2つあったことです。一つは、事業としてポートフォリオ改革を進め、2025年に半導体材料のリーディングカンパニーとなるという目標。もう一つは、レゾナックという社名の由来である「Resonate(共鳴)」とつながる「共創」という企業姿勢を伝えること。この2つの要素をどう伝えていくかが大きな課題でした。
私自身は、事業内容が伝わらなければ、企業文化や姿勢は伝わらないと考えていました。特に、「共創」というコモディティ化した言葉を懸命に伝えても、社名が知られていない会社の姿勢は人々の心には響かないのではないか、という思いが強く、まずは「人々の心に残りやすい、理解しやすいストーリー」で伝えなければならないと強く意識していました。
「日本の半導体は、材料分野では実は他国に負けていなかった」という事実は、当時まだ世の中に広く知られてませんでした。そのため私は、半導体はデバイス分野では遅れを取ったが、世界の半導体を日本の化学会社が支えているという事実をしっかりと伝えることには、きっと大きな意味があり、人々の心にも残るはずだと考えたのです。
社会文脈と経営戦略の読み解き
BtoBのコーポレートブランディングにおいては、事業内容や製品、あるいは自社が何を伝えたいかという前に、企業が経営戦略として社会の中でどのような課題に向き合い、どのような存在を目指しているのかをまず明らかにすることが重要です。業界の環境、世の中のニーズ、そしてその中で自社が取るべきポジション。これらの要素をあくまでもこの順番で読み解き、自社のストーリーを再構築することが非常に重要であると考えています。
パーパスは非常に重要だと認識していますが、それをそのままコミュニケーションとして用いてしまうと、いわば「パーパスごっこ」に陥ってしまう可能性があります。だからこそ、企業の真の存在意義、つまり社会に対して自分たちの会社がどんな役割を果たす存在なのかという根本的な問いを、もう一度経営戦略から組み直し、それをきちんと社会文脈のストーリーに落とし込んでいくことが必要だと感じました。
このように、新会社発足前の第一段階として、広報活動を強化しました。半導体電子材料のファクトブックを作成し、メディア向け勉強会を重ねるなど、きめ細やかな取り組みを進めました。その結果、新会社発足時の説明会には、従来の化学業界の記者だけでなく、半導体や電気業界の記者も来場し、コミュニケーションの土台を築くことができたと思います。
2年目以降は、AI半導体へのシフトや市場のゲームチェンジといった動きを捉え、メディア露出を拡大しました。日本の半導体が負けていない、という認識が浸透する中で、さらに次なる段階として、世界的なゲームチェンジが起きているという事実をファクトベースで丁寧に伝えていくキャンペーンを行いました。日経新聞との共同企画「半導体ミライ・アライアンス」の立ち上げや、社内の挑戦を伝えるオウンドメディア連載「アンサングリーダー」を通じて、統合による挑戦企業としてのイメージを確固たるものにしていきました。
後半のトークセッションでは、ビルコム取締役 早川がモデレーターを務め、山田様にさらに深く質問を投げかけました。
経営陣を巻き込むコミュニケーション術
ソートリーダーシップを確立し、経営陣の協力を得ることは不可欠です。「メッセージの統一や打ち出す方針への深い理解を経営陣にどう得るか」「メディア露出をスムーズに受けてもらうために、どのような協力要請をしてきたか」という参加者からの質問に対し、山田様と早川がそれぞれ語りました。
早川:山田さんにお話しいただいた取り組みは、経営陣をはじめ、他の事業責任者の皆様など、多岐にわたる関係者を巻き込みながら実行する必要があったかと思います。この点について、山田さんはいかがお考えですか?
山田:経営の理解とは、コミュニケーション施策への理解というだけではなく、経営戦略について認識をそろえることが重要だと考えています。コミュニケーション部門が経営陣の目指す方向性(経営戦略)を深く理解し、コミュニケーションの中核に据えることが、まず第一歩です。
BtoBでは、そもそもメディア露出の必要性を理解されてないこともあります。レゾナックもそうでした。このため、社内の関係部門と横軸で「半導体PR戦略プロジェクト」を立ち上げるとともに、社内の事業部門向けにニュースリリース説明会などを実施し、広報の意図を粘り強く伝え、理解を深める努力を重ねました。「半導体PR戦略プロジェクト」は、経営部門やIR部門を巻き込み、社内全体で発信するネタを掘り起こす仕組みとして構築しました。
早川:お話しいただいた中で、いくつか重要な要素があると感じていますが、その一つがストーリー構築だと思います。BtoBの領域では特にいかがでしょうか?
山田:外部から参画したからこそ、明確に気づけた点があったと思います。メディア関係者が何をどのように捉えているのかを把握し、そこからヒントを得て、試行錯誤を繰り返しながらストーリーを磨き上げていきました。過去レゾナックでは、メディアとのタイアップなどの実績がなかったんです。しかし広報施策においては、パブリシティ、タイアップ、オウンドメディアなど、360度でのメディア活用が重要です。私は新聞社での記者経験とタイアップ制作の経験から、積極的にメディアを組み合わせた施策を展開することの必要性を感じていました。特に、日経新聞のような信頼性の高い媒体が、報道だけでなくアジェンダ設定に貢献してくれることには、非常に大きな意味があると考えています。
早川:私たちビルコムも、その点は非常に重要だと考えています。課題が明確であれば、経営層が既に理解している場合もあるため、社内的な合意形成は比較的スムーズに進むこともあります。しかし、自部署が中心となって進めるべき部分においては、ストーリー設計に頭と時間を費やす必要があると感じています。特に難しいのは、それをシンプルにまとめ上げること。そのため、試行錯誤を繰り返すことが多いと私も質問しながら改めて感じました。
BtoBブランディング成功の鍵
経営戦略との一体化:企業が社会でどうあるべきか、何に向き合うのかという経営戦略を深く理解し、コミュニケーション戦略と連動させる。
意味理解を促すストーリー構築:単なる認知ではなく、「どんな会社か」を心に刻むような、文脈や意味を伴ったストーリーを丁寧に作り上げる。
広報先行の土台作り:広告に頼る前に、ファクトに基づいた情報発信でメディアや社会からの信頼と理解を得る広報活動を先行させる。
多角的なメディア活用:パブリシティ、タイアップ、オウンドメディアなど、それぞれの特性を理解し、組み合わせて効果を最大化する。
社内を巻き込むコミュニケーション:経営陣や事業部門との対話を重ね、ブランディングの意義を共有し、協力を得る体制を構築する。
ビルコムは、単なる情報発信に留まらず、データに基づいた戦略的なPR活動を通じて、企業の市場創造を支援しています。 その強みは、独自の診断技術と伝達技術にあります。
診断技術:これまで曖昧になりがちだったブランド力をデータによって可視化します。独自の指標である「PRパワー」の考え方に基づき、当社で開発・提供している広報効果測定ツール「PR Analyzer」の報道データを用いて測定。必要なPR戦略や現在の課題をデータで客観的に確認できます。感覚的だったブランドの概念を明確なデータで捉え、効果的な戦略立案に繋げています。
伝達技術:PRパワーの測定を通じて課題を明確にすることで、次に打つべき効果的なPR戦略のパターンを見出すことができます。ビルコムには20年以上蓄積されたPR戦略の豊富なノウハウがあります。広報業務に関わるデータ分析やメディア露出状況から企業のブランド課題を可視化し、数多くの成功事例に基づいた打ち手のパターンを蓄積しています。
自社の課題を把握したい、あるいはブランド力を高めたいけれど何から始めたらよいか分からない、といった場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
ビルコムへのお問い合わせはこちら
書き手:コーポレート戦略局 川島弓奈