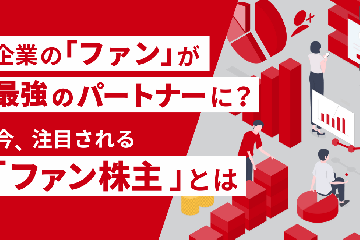PR BLOG
PRブログ
- 2025年09月03日
- PRトレンド
値上げ時代を勝ち抜く!顧客の心を掴む「体験型PR」のススメ
原材料費の高騰や円安の影響で、私たちの生活に身近な「モノ」だけでなく、レジャーやサービスといった「コト」までもが値上がりする時代になりました。
総務省が発表した2025年7月の消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)は、前年同月比で3.1%の上昇を示しており、物価上昇の波は依然として続いています。
2020年基準 消費者物価指数 全国 2025年(令和7年)7月分
このような市場環境下で、BtoC企業のブランドマネージャーやマーケティング担当者は、以下のような課題をお持ちではないでしょうか?
- 度重なる値上げで、顧客が離れてしまうのではないか?
- 価格競争に巻き込まれ、ブランドの価値が毀損してしまうのではないか?
- どうすれば、自社の商品を選び続けてもらえるのか?
その答えは、顧客との間に「価格」以外の強い結びつきである「共感」や「愛着」といったエンゲージメントを構築することにあります。その有効な手段のひとつが「体験型PR」です。
市場インサイト:なぜ今、「体験型PR」が重要なのか?
終わらない値上げラッシュは、消費者の行動に大きな変化をもたらしています。
2025年4月にデロイト トーマツが行った「国内消費者意識・購買行動調査」によると、「消費金額が増えた/大幅に増えた」と回答した割合が、ここ数年増加傾向にあり、特に食料品ではこの傾向が顕著に現れています。その理由として6割以上が「物価高」を挙げています。また、CCCMKホールディングス株式会社が行った「2024年消費意識調査」では、95%の人が「物価が上がった」と実感しており、生活者の節約意識は非常に高まっています。
しかし、興味深いのは人々がただ単に支出を切り詰めているわけではない、という点です。同調査では、節約する分野がある一方で、旅行や趣味、推し活といった自分の価値観に合う「コト」には積極的にお金を使いたいという「メリハリ消費」の傾向も明らかになっています。
【2024年消費意識調査】生活者約1,700人に聞いた!物価上昇のなか、収入・消費の本音とは
これは、消費の価値基準がモノを所有することから、そこでしか得られない特別な「体験」をすることへとシフトしていることを示しています。
体験型PRは、このような消費者のインサイトに応えるものです。顧客がブランドの世界観に直接触れ、商品を五感で楽しむ機会を創出します。この「リアルな体験」は、Webサイトや広告だけでは伝えきれない商品の魅力を深く理解してもらうことを可能にし、消費者の心に強い印象を残します。その結果、ブランドへの共感や愛着が深まり、価格に左右されない顧客ロイヤルティを育むことができるのです。
成功事例から学ぶ「体験型PR」のチカラ
多くの先進的なBtoC企業が体験型PRに注力し、大きな成果を上げています。ここでは、3つの象徴的な事例をご紹介します。
事例1:味の素株式会社 “塩の新たな価値”を発見する焼肉食べ比べイベント
同社が行った「夏休みの自宅での食事傾向」に関する調査では、物価高の影響により約2人に1人が外食の頻度が減ったと回答。その中でも、控えている外食の1位が「焼肉」である実態が明らかになりました。一方で、「おうち焼肉」に満足していない人も多く、不満を持つ人のうち「肉の食感がかたい」との声が約7割を超えるというインサイトが得られました。
この「外で焼肉を楽しみたいけれど、我慢している」「家でやってもお店のように美味しくない」という生活者のリアルな悩みを解決するために、驚きの体験イベントを発表しました。ロングセラー商品である塩「瀬戸のほんじお」を使い、塩水に肉を漬け込むだけで肉が柔らかくなる新調理法を、参加費わずか3円で体験できる「焼き肉食べ比べイベント」として開催しました。
参加者は「ほんの少しの手間で、お肉がこんなに柔らかくなるのか!」という驚きと発見を自身で直接体験します。こうしたインパクトのある体験は、「塩で肉を柔らかくする」という新しい知識を記憶に刻みつけ、消費者の中にある「塩=味付けに使うもの」という固定観念を覆すことができます。言葉で説明するよりも実際に食べ比べてもらうことで、製品の新たな価値を強く伝えています。調査データで示された多くの人が抱える悩みを「自分ごと」として捉え、その解決策を驚きや発見と共に体感することで、家庭での実践や商品の購買へと繋がる動機付けになります。
事例2:味の素グループ “食の未来”を旅する「食のワンダーランド」
2025年3月に行われた、味の素グループの春季の新製品説明会では、単なる商品説明の場に留まらないユニークな体験が提供されました。「食のワンダーランド2025年春」と題したこのイベントは、「味の素中学校」をテーマに、味の素グループ社員が教員に扮し、中学校の授業に見立てて各製品の説明を行いました。新製品説明後は、文化祭をイメージした試食ブースを設置し、食の楽しさや未来の可能性を示唆しました。
単に製品紹介や機能を伝えるだけでは、ブランドが目指す未来や世界観まで伝えることは困難です。しかし、人々をワクワクさせる体験は、製品がもたらす本質的な価値を直感的に伝えることができます。参加者は受け身で説明を聞くのではなく、楽しみながら製品の魅力や開発ストーリーに没入します。こうした特別な体験は、製品への深い理解と共感を呼び、参加者自身が「伝えたい」と感じる熱量(口コミ)を生み出します。
事例3:雪印メグミルク株式会社「さけるチーズフェス」
独特の食感とさいて食べる楽しさが人気の「さけるチーズ」。その魅力を最大限に伝えるために、雪印メグミルクはファン参加型のイベント「さけるチーズフェス」を2025年3月に開催しました。
「世界一楽しいチーズ」を目指します!3(さ)月9(く)日「さけるチーズの日」に「さけるチーズフェス2025」開催乙葉さん登壇のトークイベント、親子で楽しめるオリジナルコンテンツが盛り沢山!
ステージでは〇✕クイズ大会が行われたり、発売中の6種類の「さけるチーズ」を食べ比べができるセットがあったりと、参加者が楽しめるコンテンツが提供されました。景品としてチーズを細かくさける「ボンバーカッター」がプレゼントされ、参加者は「さく」という行為の奥深さや楽しさを再発見。既存ファンだけでなく、新たな顧客層にも商品の魅力が伝わりました。ファンとの直接的なコミュニケーションは、ブランドへの愛着をより一層強いものにしています。
「体験」を通じて、ブランドの物語を顧客と共に創る
これらの事例に共通しているのは、企業が一方的に情報を発信するのではなく、顧客を巻き込み、共にブランドの価値を創り上げている点です。
値上げという現実があるからこそ、顧客は「なぜ、この商品を選ぶのか?」という意味を求めています。体験型PRは、その意味を顧客自身の「楽しい」「嬉しい」「特別だ」というポジティブな感情と共に提供できる、有効なコミュニケーション手法だと考えられます。
ビルコムは、単なる情報発信に留まらず、データに基づいた戦略的なPR活動を通じて、企業の市場創造を支援しています。 その強みは、独自の診断技術と伝達技術にあります。
診断技術:これまで曖昧になりがちだったブランド力をデータによって可視化します。独自の指標である「PRパワー」の考え方に基づき、当社で開発・提供している広報効果測定ツール「PR Analyzer」の報道データを用いて測定。必要なPR戦略や現在の課題をデータで客観的に確認できます。感覚的だったブランドの概念を明確なデータで捉え、効果的な戦略立案に繋げています。
伝達技術:PRパワーの測定を通じて課題を明確にすることで、次に打つべき効果的なPR戦略のパターンを見出すことができます。ビルコムには20年以上蓄積されたPR戦略の豊富なノウハウがあります。広報業務に関わるデータ分析やメディア露出状況から企業のブランド課題を可視化し、数多くの成功事例に基づいた打ち手のパターンを蓄積しています。
自社の課題を把握したい、あるいはブランド力を高めたいけれど何から始めたらよいか分からない、といった場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
ビルコムへのお問い合わせはこちら
書き手:コーポレート戦略局 川島弓奈