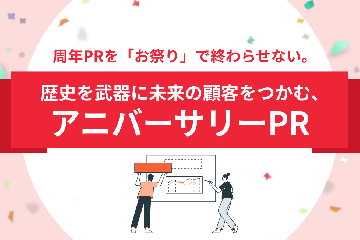PR BLOG
PRブログ
- 2020年08月19日
- PRトレンド 、PRノウハウ
コロナ禍の広報成果の振り返り、どうすべき?今こそ必要な効果測定とは
2020年上期の振り返り時期を迎える広報担当の方も多いでしょう。コロナ禍の影響が長期化する中「この半期の広報成果をどう振り返るべきなのか」と悩む方も少なくないはずです。
<よくあるお悩み>
・コロナ禍の報道量増加に押され、自社の報道件数は前年比マイナスに。市況を踏まえた評価はできないか?
・炎上してしまった案件と、うまく行った案件が混在しているが、件数や広告換算費だと切り分けができない。どう可視化すると分かりやすいのか?
・リモートとなり紙媒体の成果を出社しないと確認できず、成果の収集に時間がかかっている。業務フロー自体を見直していきたい
本記事では、こうしたお悩みに対するヒントをお伝えします。
<目次>
- 件数や換算費だけの効果測定は、そもそも不十分
- ニューノーマルに取り入れるべき指標例
- 量の成果は、質と掛け合わせた評価が必要
- テレワークはクリッピング業務の見直しどき
- 世の中の変化に合わせた効果測定を実施しよう
件数や換算費だけの効果測定は、そもそも不十分
弊社が広報・PRの効果測定ツール「PR Analyzer®」を提供する中で、現在導入している効果測定指標を聞いたところ「掲載件数・広告換算費」がトップです。
しかし、これらの指標を単体で見ると、いくつかの問題点があります。
・SNSやwebニュースの影響力が上がる一方、webは広告換算費としては紙・テレビより少額となりやすく、適切な成果評価ができない
・炎上で報道量が増えたなどのネガティブ露出を件数・広告換算費では可視化できない
もちろん広報部門を立ち上げたばかりの企業にとって、件数をKPIとして発信・掲載量を上げていくことは不可欠です。しかし一定のアクション量が担保されてきたフェーズにおいては、件数や換算費だけでなく、記事の質やSNS拡散量などを含んだ、複数指標で成果を可視化していくことが必要です。
※こうした効果測定のキホンについては、定期セミナーを開催しております。もっと知りたい方はぜひご参加ください。
ニューノーマルに取り入れるべき指標例
コロナ禍など、市況に大きな変化が見られた時は特に、複数指標で成果を可視化することで、適切に活動を振り返ることができます。いくつかの指標例を紹介します。
シェアオブボイス
露出量を前期と比較するだけだと、災害などの外部要因の影響で大きく数が増減することもあります。しかし、同状況下での他社との量的な比較(=シェアオブボイス)により、競合他社に比べて効果的な活動が実施できたかという視点から、成果を可視化することができます。
例)PR Analyzer®で、4つのキャッシュレス決済サービスの報道量を比べた例
参考記事)https://www.wantedly.com/companies/bilcom/post_articles/148868
SNSシェア/言及
コロナ禍で、SNSをチェックする時間は増加傾向にあります。スカパー!の調査では、緊急事態宣言発出前後の「SNS」利用時間の変化は、平均21分増、10代では平均53分増という結果も出ていました。
特に若い世代がターゲットの企業では、SNSでどう自社が語られているかを把握し、情報発信の戦略を立てていく必要があります。
コロナ禍に限らず日常的に、シェアオブボイスの測定に加え、競合のSNS波及をチェックすることは、こうした戦略のヒントになるでしょう。自社・他社含め、SNSで波及した記事のテーマや媒体を見ていくことで、注力するテーマや情報提供を強化すべきメディアを検討することができます。
<SNS波及数を分析した例>

量の成果は、質と掛け合わせた評価が必要
冒頭でお伝えしたように、件数や広告換算費をKPIとすることも、広報フェーズの初期には必要でしょう。しかしこれらの量的KPIだけでは、内容の質は可視化できず、改善につなぐことができません。
ビルコムではPRの取り組みフェーズを4つに分けていますが、量強化フェーズが安定してきたら、「質」を測る指標もKPIに取り入れることを勧めています。
特に現在の広報では、目にする機会を増やして認知を獲得するだけではなく、その掲載内容がターゲットの心に刺さり、良いブランドとして共感を産んだかという点が重要になりつつあります。
質を測る指標は課題によって様々です。
例)
重点媒体:ターゲットに響く媒体を洗い出し「重点媒体」として、掲載件数のうち重点媒体の比率を見ていきます。アクション量が十分だが、アウトプットの掲載の内容がイマイチという課題がある場合などに効果的です。
内容分類:目指すブランドと生活者の認知の乖離がある場合は、注力するテーマを決め、その記事にテーマが盛り込まれているかという内容分類を行い、割合を見ていくのも良いでしょう。
論調分析:炎上した過去がある場合、「論調がポジティブかネガティブか」という論調分析を取り入れ、ポジティブ比率を見ていくこともできるでしょう。
全体量を右肩上がりにすることだけが広報活動ではありません。他社と比べ優位な露出量をキープしながら、質に注力するというのも一つの戦略です。
テレワークはクリッピング業務の見直しどき
コロナ禍ゆえの悩みとして活動の評価手法についてお伝えしてきました。
それ以外の悩みとして、「コロナ禍が想定以上に長期化し、クリッピングをオンライン化したい」という相談をいただくことが増えています。
これまで毎朝、自分たちで媒体を確認してクリッピングを行なっていたが、出社回数を減らすこととなり、これまでの業務フローを見直さなくてはならないというのです。
広報・PRの効果測定ツール「PR Analyzer®」は、量・質合わせた8つの指標をオンライン上で自動収集および一元管理できるツールです。ニューノーマルの効果測定において、新たな手法にご興味ある方は、是非お問い合わせください。
世の中の変化に合わせた効果測定を実施しよう
常に世の中の変化と対面する広報部門。
コロナ禍だけではなく、今後起き得るあらゆる災害時を想定して、効果測定の体制も多面的に設計しておくことが重要です。
・同一基準で質・量を計測し、時系列で評価する/p>
・同時期の競合の露出把握をすることで、相対的な評価を行う
・SNS波及など、時代に合わせた評価を取り入れる
これらの視点で、下期以降の効果測定の体制を見直しませんか?
※PR Analyzer®では、広報の効果測定に関する個別相談会も実施しています。
ご興味ある方は「個別相談会希望」と記載の上、ご連絡ください。