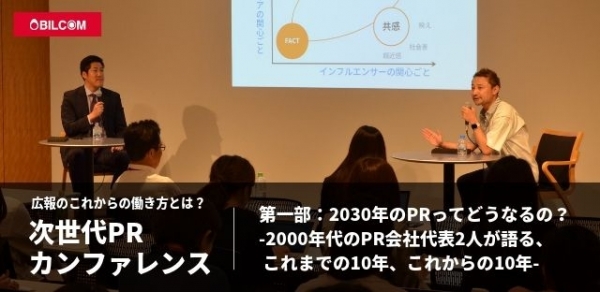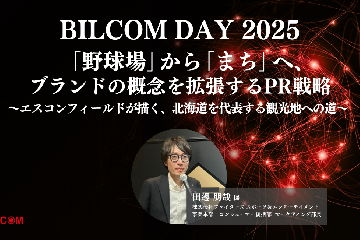PR BLOG
PRブログ
- 2019年07月02日
- セミナーレポート
メディアはこれからどうなる?withnews・奥山編集長が見つめるメディアの未来とは

2019年6月6日に開催した「広報のこれからの働き方とは?次世代PRカンファレンス」。約100名の方にご来場いただき、大盛況の中で幕を閉じました。第一部ではブルーカレント・本田哲也氏、第二部では朝日新聞社 withnews編集長・奥山晶二郎氏をゲストとしてお迎え。これからの広報の働き方、メディアのあり方について熱い議論が交わされました。今回は第二部の様子をお届けします。
★第一部の様子は下記をご覧ください。
https://www.bil.jp/blog/2019/07/conference01.html
第二部:メディアのあり方はどう変わる? -朝日新聞社のデジタル化をけん引する withnews編集⾧が見るメディアの未来-
朝日新聞社の記者だった奥山氏は、2007年に自ら手を挙げ、デジタルを担当する部署に異動。以降、新聞社のデジタル領域で様々な挑戦をされています。このセッションではビルコム取締役・早川がモデレーターとなり、奥山氏が考えるメディアの未来を語っていただきました。
■登壇者
朝日新聞社 withnews編集長
奥山晶二郎氏

ビルコム株式会社 取締役
早川くらら

■目次
・withnewsは、世の中が感じている"もやもや"を丁寧に可視化する
・Webも紙も "パッケージ"で勝負する時代
・オウンドメディアは指標を独自に設定して評価をすべき
・記者と広報・PR担当者は、一方通行ではない関係性を築こう
・まとめ:カンファレンスを終えて
withnewsは、世の中が感じている"もやもや"を丁寧に可視化する
(奥山氏:以下、敬称略)まず、withnewsの紹介をさせていただきます。日本のマスメディアがデジタル化にどう対応してきたか、というところに繋がる部分もあるかと思います。

withnewsのPC版トップ画面
(奥山)まず、これがPC版サイトの画面ですが、色々な記事を載せています。負け惜しみではないんですが、まとまりがないことが狙いのひとつでもあります。新聞ではできないことを模索していく中で、このようなスタイルに行き着きました。
色々な記事がありますが、ネットの話題をきちんと取材することには特に力を入れています。これは、今まで新聞社にはなかった視点でもあると思っています。自分たちが課題を設定するのではなく、既に世の中が関心を持っていること自体にニュースバリューがあるのではないか、という発想です。
ただ、情報発信の手段自体はコモディティ化しているので、ただ発信するだけでは希少性が発揮できない。ですので、世の中の関心ゴトと取材を組み合わせて、withnewsらしさを出しています。
(奥山)そして、「普通の人」にあえて取材をする企画にも取り組んでいまして、最近はYahoo!トピックスに転載されるなどしてよく読まれています。
マスメディアは事件やイベントが起こってから取材をすることが多いのですが、世の中には静かに、ひたひたと積み重なっている課題感もあると思っています。
例えば、子育てや転勤に対する不安などです。大きなニュースではないけれど、みんなが感じているもやもやを、もう少し可視化できないかなと思ってチャレンジしています。

(奥山)次も、世の中の関心ゴトから着想を得た記事です。
これはTwitterなどでバズった記事なんですが、パキスタン人のゲーマーが鉄拳ゲームの世界大会でいきなり優勝したんですね。そのときに「俺の国には俺より強いやつがもっといる」と、少年漫画みたいな台詞を喋って(笑)それがツイッターでバズってたんですよ。
朝日新聞はパキスタンに記者がいるので、「これ取材してみない?」と話したら面白がってくれて、イスラムバードの支局長が取材に行ったんです。
すごく柔らかいテーマですけど、中国がパキスタンを支援していること、人口が急激に伸びていることなど、背景は結構しっかりしていて。Twitterには「勉強になった」という反応もあったりと、僕らとしても読者がこれほど興味を示してくれるのが意外でした。
このように取材は丁寧にやりつつ、取材のアプローチやテーマも含め、今の時代に合うものを試行錯誤しているのは、withnewsの特徴と言えると思います。
(奥山)withnewsが独自機能として行っているのが、「取材リクエスト」です。世の中の方が感じているもやもや感は、我々が課題設定するよりも聞いたほうが早いのでは、ということで、取材してほしいネタを読者から募集しています。
コンテンツの価値は、ファクトの大きさだけではない気がするんですよね。取材した結果だけでなく、結果に至るまでの経緯―例えば、取材のきっかけから既にストーリーが始まるような記事が生まれると面白いなと思って取り組んでいます。
Webも紙も "パッケージ"で勝負する時代
(早川)ここからは、withnewsだけの話にとどまらず、メディア全般の話も含めて聞いていきたいと思います。色々なメディアや記事をご覧になられて、何か新たな報道や編集の傾向を感じているポイントはありますか?
(奥山)一周まわって、Webと紙が近づいている気はしています。一本の記事だけで勝負するのは、もう限界なのでは、と思っていて。メディアが、ある世界観を持つひとつのパッケージとして読者と繋がることを突き詰めると、結局紙面の構成と同じになるんですよね。
ただ、インフラ的な存在になるのか、そのメディアにしかない尖ったものや希少性をかたちにするのか、というのは慎重に判断しないといけません。
一強多弱がデジタルの常でもあるので、その方向性がうまく噛み合えば、コンテンツプロバイダーとしては働きやすい時代に入っていると感じています。
ちょっと煽る言い方をすると「コンテンツで商売をする未来は無いのでは」と考えています。
そもそも紙の時代はどうだったかと考えると、紙の新聞は月額購読の"サービス"としての商品だったと改めて思うんです。読者は明日の新聞に何が載るかわからないのにお金を払ってくれて、それって実はコンテンツで稼いでいたわけではないんじゃないか、と。
毎日郵便受けに届く安心感や、「隣の人が購読しているからウチも購読しないとかっこ悪い」という同調圧力、たまにくれるビール券。このような要素の総合パッケージサービスだとしたら、それは紙でもWebでも関係ないですよね。

(奥山)先日、ある企業様のプロモーション案件をご支援しまして、その記事はwithnewsではなく紙面に掲載されました。withnewsに露出の場をつくるのではなく、編集力を商品として提供したんです。
他にもスポーツ選手やタレントさんのキャスティングもご支援させていただきましたが、これは媒体の新しい役割を開拓できたのではないかな、と思っています。
(早川)なるほど、コンテンツではなくパッケージで勝負する時代だと。
編集力という話もでましたので、記事の在り方についても、少し伺ってみたいです。
デジタルだとPVなどが全て数字で見えてしまいますよね。ともすれば、「PVが高い記事を書こう」という方に進んでしまうこともあると思います。
一時期はPVを偏重している、という議論も起こりました。PVも大事ではあると思うんですが、withnewsではどういった観点で記事を選定していますか?
(奥山)withnewsは月間4000万~5000万PVくらいで、特徴としては記事本数がすごく少ないんです。1日2-3本、月100本くらいの規模感ですが、おそらく記事の本数を2倍に増やしても、PVは2倍にはならないと思うんです。
PVや記事本数の最低ラインの見極めも大事なんですけど、その先は数じゃない戦いが始まりますよね。
例えば、Yahoo!ニュースさんは月間約160億PVなんですね。月間10億PVの単体メディアってないんですよ。
朝日新聞デジタルで2~3億PVくらいで、5億も難しい。そうなると、おそらく各媒体が自分でものさしを作った方がいいんだろうな、と思います。
オウンドメディアは指標を独自に設定して評価をすべき
(早川)"ものさし"というところで質問なのですが、今は企業がオウンドメディアやソーシャルメディアを運営することも多いです。
とりあえず運用しているけど、労力もかかるし、今後どうしていけばいいかわからないという声も聞きます。企業がメディアを運営する際は、どんな目標をたてればいいんでしょうか?
(奥山)先日、SHARP公式Twitterの中の方と話す機会があったんですが、あのレベルは再現性がなかなか難しいな、と思っています。あれ、ほとんど彼の芸なので。
一方で、目標設定も大事なのだろうと思います。SHARPのようなオウンドを目標にすると多分難しいんですが、違う目標設定はいっぱいあるはずで。PV、UU、滞在時間、ペルソナ、回遊率など、このような指標をまずは丁寧に見た方がいいだろう、とは思います。
ただ、上層部の方に稟議がまわっていくと「意味があるの?」というツッコミがどんどん出てきてしまう、という現実があるのも事実です。でも、それぞれに目標は百通りあると思いますよ。
(早川)今のお話をうかがって、数字の部分での定量的な目標設定も大事だと思いましたし、もうひとつは「どういうことを世の中に発信していきたいメディアなのか」という編集方針をある程度定義しておくことも重要だと思いました。
withnewsでは、多くの記者に対して編集方針をどのように浸透させているんですか?

(奥山)現場には、「連載を書きませんか?」とよく言っています。一本の記事だけだと、消費されて終わってしまう傾向が強いのですが、3回連載でも上下でもパッケージにすると、発信者の顔が見えるようになります。
すると、その先にはメディアが―これはオウンドメディアにも通じると思うんですが、単なる情報発信の存在ではなく、サービスとして存在できるようになると考えています。
困っている人がいて、その課題を解決する手段くらいの上位レイヤーにメディアを存在させられたら、月間100万PVのメディアでも良い気はしています。
記者と広報・PR担当者は、一方通行ではない関係性を築こう
(早川)メディアが変化を続ける中で、広報やマーケティング担当者はこれまでの考え方をどのように変えていけばいいと思いますか?
(奥山)ひとつ言えるのは、今はBCCの一斉送信メールでは想いが届かない、難しい時代になってきた、ということでしょうか。とはいえ、「個別に連絡してよ」と言うのはおこがましいですし、そんな暇は無い、というのが現場の声だと思います。
それでもマスメディアの"マス"の部分はどんどんコモディティ化しているので、タレントさんが出る新商品発表会など、「とりあえず抑えておく」ネタへの期待値や存在感はどんどん少なくなっている気はしています。
自分に関係ないと思うものをスルーするのは今の時代のデフォルト構造になっているので、「あなたに関係がありますよ」というかたちで伝えていただくのは、負荷との兼ね合いですが、今後ますます大事なのではないかと思います。
(早川)なるほど。理想としては、1to1マーケティングくらい届ける情報は変えた方がいいんでしょうけど、実際はリソースの問題もあって難しい部分も出てきますよね。
当社では日々メディアさんのニーズをうかがっていますので、プレスリリースをお送りしたあとに「この間こんなお話しをされていたので、こういう切り口はどうでしょう?」と補足でご連絡をさせていただくこともあります。
メディアや記者の思考を理解して、「だからこの情報を届けたんです」と伝えていくのは、地道ですがすごく大事なことですよね。
一方で、情報を受け取るメディア側からすると、プレスリリースが届く際の理想のかたちや、広報担当者との関係性はあるんでしょうか?

(奥山)なかなか悩ましいんですが、「一方通行の関係じゃない」というのはひとつ理想として言えると思います。
その関係値づくりが、まさにこういうセミナーでの出会いなどでワンクッションあるといいですよね。フラットなところで知り合えると、提案の選択幅が広がると思うんです。
プロダクトありきで知り合うと、それ以外の選択肢がお互いに見えなくなってしまう。ある意味不幸というか、もったいない出会いになってしまいます。
何のためにPRをするのか、何のために記事を書くのか、というのはニアリーイコールになっていると思うんです。記者個人としても、媒体としても、専門や得意なアプローチがある。ですので、大変おこがましいのですが、ひょっとしたらそこをくすぐるような出会いを意識していただけるといいのではないかな、と思います。
個人的に嬉しいのは、「プロダクトのダイレクトなPRじゃなくても、世の中のこんな課題が可視化できたらいいと思うので、ご紹介しました。」という案件。すると、「こういう切り口だったらご対応できますか?」という会話が始まります。
(早川)確かに、記者さん一人ひとりの好みもかなり多様化してきているとは感じます。媒体や社会のトレンドも含めて、そこをキャッチアップして、適切な情報を提供したり、ディスカッションしたりできると、双方にとって意味のある関係性がつくれるかもしれないですね。
カンファレンスを終えて
メディアが大きく変化していく中で、わたしたち広報・PR担当者も時代に合わせ、思考や手法を適応させていくことが求められています。そのためには、メディアや生活者の最新動向を逐一キャッチし、記者やディレクター一人ひとりとコミュニケーションをとっていくことが必要です。
ビルコムでは、ジャンルを問わず、日々メディアの皆さまと情報交換をしながら企画のご提案を行っています。広報・PRに関するお悩みをお持ちの方は、お気軽に問い合わせください。
(書き手・ビルコム株式会社 高橋)
★この記事を読んだ方におすすめのコンテンツはこちら
1:ファクトとビジュアルがキー!?2019年カンヌライオンズ受賞作から見る最新のPR潮流とは
2:記者発表会で理想のメディア掲載を創出するための6つのポイント
3:ニュースになるプレスリリースの書き方とは?~広報の基本であるプレスリリースを、より効果的なものにするポイント~
★第一部の様子は下記をご覧ください。